不動産投資を始めたばかりの方によくあるトラブルを3つ紹介します。
トラブルを避ける方法も併せて記載しますので、これから不動産投資を始めようという方は必ずお読みください。
不動産投資トラブル1:占有者トラブル
不動産を実質的に支配している状態にある人のことを「占有者」といいます。所有者以外にも当てはまり、例えばアパートの入居者なども占有者になり得ます。
立ち退きが必要になって占有者と揉めるケースはよくあるトラブルのひとつですので、初めての投資は空き家に絞って選ぶようにするのがリスクを低減することになります。
不動産投資トラブル2:重要事項説明トラブル
重要事項説明は専門的な内容も多いため、消費者がよく理解しないまま契約を進めてトラブルに陥るケースがよくあります。
稀に悪意をもった事業者が「ちゃんと説明しました」、「契約後は自己責任です」という態度で不利な契約に持ち込ませようとすることがあります。
以下の3つの点を確認してトラブルを避けられるように備えましょう。
1.建物取引士の免許証を確認
2.契約解除の方法を確認
3.リスクに関する記載が説明書内にあるかを確認
1.建物取引士の免許証を確認
重要事項説明の際には、宅地建物取引士が免許証を提示することが義務付けられています。
稀に資格を持たない営業担当者がそのまま説明しようとするケースがあるため、説明を受ける前に免許証の提示がきちんとされているかを確認してください。
2.契約解除の方法を確認
基本的には不動産物件の引き渡しが完了するまでは解約があります。これに関する説明が曖昧だったり、説明が割愛されたりする場合には注意が必要です。
「クーリングオフ」という言葉で安心させようとするケースもありますが、契約によってクーリングオフ制度が適用されないことがあるので自分で条件を確認することが大切です。
3.リスクに関する記載が説明書内にあるかを確認
説明された内容と契約書面に記載された内容が異なるためにトラブルが起きるケースがあります。
例えば「家賃保証してくれると言われて契約したが、実際には2年ごとに家賃が見直される契約だった」というトラブルはアパート経営の契約などにおいてよくあります。
口頭で受けた説明は後で証明することが難しいため、必ずすべて説明書内に記載があるか、内容に齟齬(そご)がないかを確認しましょう。
不動産投資トラブル3:不動産投資詐欺トラブル
特に不動産投資初心者に対して、価格の合わない契約を交わさせたり、代金を持ち逃げしたりする詐欺が後を絶ちません。
国民生活センターの発表によると、2018年度の被害相談件数は1,300件を超えたそうです。
不動産投資詐欺の代表的な4つの手口とそれを避ける方法をチェックしておきましょう。
1.手付金詐欺
2.満室偽装詐欺
3.二重譲渡詐欺
4.家賃保証・空室保障詐欺
1.手付金詐欺
契約の前に「仮押さえしたほうがいい」などと言って手付金を要求し、そのまま持ち逃げする詐欺です。
手付金を要求されても焦らずに検討したい旨を伝え、しっかりと検討しましょう。
2.満室偽装詐欺
実際には空室だらけの物件がさも満室であるかのように偽装し、満室時の高利回りをちらつかせて契約させる詐欺です。
入居者がいる物件は必ずいつから入居しているのかを確認しましょう。直近で不自然な入居が連続しているような場合は注意が必要です。
3.二重譲渡詐欺
第三者が同じ物件の登記を自分よりも先に済ませてしまった場合、もし代金を支払っていても物件を手に入れることはできなくなってしまいます。
決済をする前に必ず登記簿の内容を確認し、不審な点がないか確認しましょう。司法書士などに依頼すると確実です。
4.家賃保証・空室保障詐欺
家賃保証・空室保障・サブリースとは、不動産事業者がオーナーから物件を一括で借り上げてくれる仕組みです。
ただし、免責事項や手数料などが著しくオーナーに不利な設定になっている詐欺があるため、デメリットに関する説明を詳細に確認しましょう。
不動産投資のトラブルを避ける3つの方法
不動産投資トラブルは特に初心者に起こりがちです。
トラブルを避けるための王道はありませんので、以下の3点を徹底して実行しましょう。
方法1.不動産投資の知識を身につける
何が正しいのかを自分で判断できるようになりましょう。
「十分に理解しない」、「甘い言葉にだまされる」ことがトラブルに陥る原因です。
方法2.信頼できる不動産会社に相談する
もっとも確実なのは信頼できるパートナーに相談することです。
実績や知名度を確認したり、極端に手数料が安かったりしないかを見れば悪意のある事業者を避けることができます。
方法3.不動産投資の経験者とコネクションを持つ
信頼できる個人やコミュニティーから「生の声」を聞くことも重要です。
投資家の目線で忌憚のない意見をもらえるコネクションをつくりましょう。
まとめ
不動産投資を始めたばかりの方によくあるトラブルを3つご紹介いたしました。
事前に対策を練り、トラブルの発生を避けることが最も重要ですので、ぜひご参考ください。



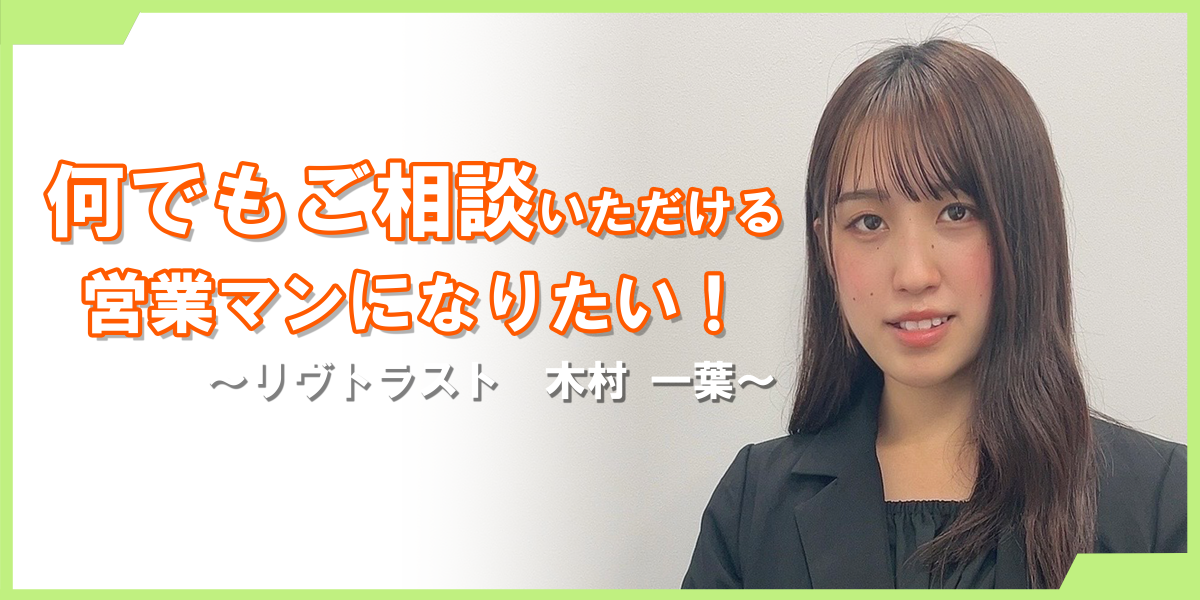
.png)