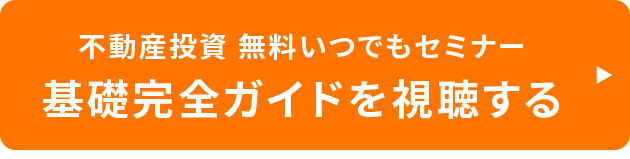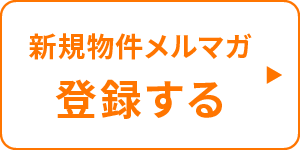「この先の10年間は、株式よりも債券投資を重視すべき」
こんな衝撃的なレポートを発表したのは、世界最大級の資産運用会社であるバンガードです。具体的には、株式30%・債券70%の資産配分を推奨しています。
しかし、これは全ての人に共通する「万能な最適解」ではありません。この記事では、なぜバンガードが「株より債券」と警告するのか、その背景にある「米国株の割高感」を示す3つのシグナルを解説します。そして、この予測に対して、個人投資家が「自分のリスク許容度」と「投資期間」に合わせた資産配分をどう見直すべきか、具体的なチェックリストと手順で徹底解説します。
なぜ「株より債券」なのか—割高を示す3つのシグナル
バンガードが「株より債券」と警鐘を鳴らす理由は、今の米国株式市場が歴史的に見て「割高な水準」にあると判断しているためです。具体的には、以下の3つの指標が、株式市場の過熱感を示唆しています。
10年期待リターンの現実値—株3.3–5.3%、債券4–5%
バンガードは、これら指標の割高感から、今後10年間のリターン予測を以下のように見込んでいます。
【バンガードの10年期待リターン予測】
・米国株: 年平均 3.3 〜 5.3%
・債 券: 年平均 4 〜 5%
この予測だけを見ると、確かに債券の方が有利に見えます。ただし、バンガード自身も、これらの予測は「中央値」であり、未来にはブレ幅があることを強調しています。また、「これはあくまで10年間の予測であり、30年以上の長期投資では株式が債券を上回る可能性が高い」とも明言しています。
「株30:債券70」は誰向け?—年齢ではなく“家計耐性×目的×期間”
バンガードが推奨する「株式30%・債券70%」という資産配分は、決して万人に適しているわけではありません。これは年齢だけで決まるものではなく、個人の「家計の耐性」「投資の目的」「投資期間」によって大きく異なります。
- 生活防衛資金・現金比率の基準: 大前提として「生活防衛資金(生活費6ヶ月分以上)」を確保できているかを確認しましょう。これがなければ、いかに優れたポートフォリオを組んでも、急な出費で資産を切り崩すことになりかねません。
- 目的別(老後/教育/住宅頭金)と拘束期間: 投資の目的が「老後資金(30年後)」なのか、「教育資金(5年後)」なのかによって、取れるリスクは全く異なります。資金を使うまでの「拘束期間」が短いほど、リスクの低い債券や現金の比率を高めるべきです。
- 収入安定性・暴落時メンタル耐性: 収入は安定していますか?また、株価が大きく暴落した時に、「冷静に買い増しできるメンタル」があるかどうかも重要です。「夜も眠れないほど不安になる」ようなら、リスク許容度を超えている証拠です。
今すぐできる“過熱相場の安全運転”—配分見直しの手順
現在の株式市場の過熱感を受け、アクセルを踏みすぎないための「安全運転」として、以下の手順で資産配分を見直しましょう。
STEP 1リスク許容度をチェックする
次の質問にYESかNOで答えてみてください。
- ✅株価が10〜20%下落した場合でも、冷静に買い増しできますか?
- ✅生活費6ヶ月分以上の現金を確保していますか?
- ✅ポートフォリオ全体のリスク資産の比率を明確に把握していますか?
- ✅万が一、資産全体が40%下落しても、生活やメンタルに支障がない範囲ですか?
- ✅投資の目的(何のために、いつまでに)と期間を明確に整理していますか?
→「NO」が多い場合は、今の投資比率を少し見直し、債券や現金比率を増やす選択肢を検討しましょう。
STEP 2ポートフォリオを棚卸しする
現在、自分がどのような資産(株式、債券、現金、不動産など)をどれくらいの割合で保有しているか、正確に把握しましょう。
STEP 3“なだらか”に調整する
「今すぐ全資産を債券に!」と焦る必要はありません。「定率リバランス」や「新規資金の債券寄せ」など、時間をかけて調整していくのが賢明です。
STEP 4行動ルールを言語化する
「株価が〇〇%下落したら買い増す」といった具体的な行動ルールを紙に書いて言語化しておきましょう。感情に流されず、ルールに基づいて行動することが、長期的な成功に繋がります。
個人投資家の優位性—「現金を持てる」という戦略オプション
バンガードのような運用会社は、顧客から預かった資金を常に運用し、毎年利益を上げることを求められます。そのため、相場が過熱していても、現金比率を高く保つという戦略は取りにくいのが実情です。
しかし、私たち個人投資家は違います。誰からも成果を問われないため、「現金を持ち続ける」という戦略を取れる大きな強みがあります。株価が高い今、あえて「待つ」という選択肢は、個人投資家だからこそ許される賢い戦略です。現金は「将来の買い時という機会を買う保険」にもなります。
よくある疑問(FAQ)
Q:今すぐ債券70%にすべき?
A:いいえ、バンガードの推奨はあくまで一般的なモデルです。あなたの「投資期間」「目的」「リスク許容度」を総合的に判断し、最適な配分を決めましょう。焦って変更する必要はありません。
Q:NISAの枠配分は?
A:NISAの非課税投資枠は非常に貴重です。長期的なリターンを最大化するため、長期投資枠(つみたて投資枠)では全世界株式や米国株式のインデックスファンドをコアに据えるのが一般的です。債券は課税口座でも運用可能なので、NISA枠とのバランスを考慮しましょう。
まとめ—“予測”よりも“耐性設計”。高値圏の今こそ、腹落ちした配分へ
バンガードの「次の10年は株より債券」という予測は、私たち個人投資家が「今の市場環境で、どう資産を守り、育てるか」を考える良い機会を与えてくれています。重要なのは、予測に振り回されるのではなく、情報を元に、「自分のリスク許容度」と「投資目的・期間」に合わせた資産配分の“耐性設計”をすることです。
市場が最高値を更新している今だからこそ、感情に流されず、冷静に自分のポートフォリオを見直し、腹落ちした行動ルールを確立しておきましょう。それが、将来訪れるであろうあらゆる相場変動を乗り越えるための、最も賢い戦略です。
無料セミナーでは、最新の金利情報から、不動産投資の基礎、そして具体的な物件選びのポイントまで、資産形成に役立つ知識を分かりやすく解説しています。


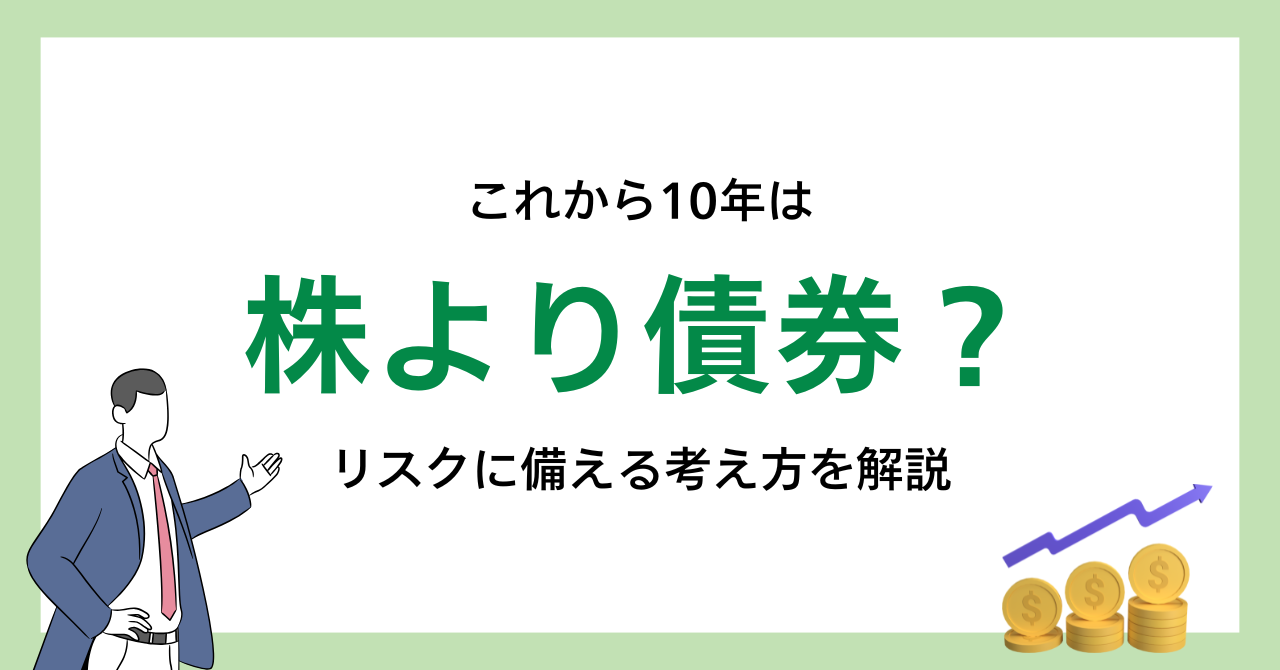
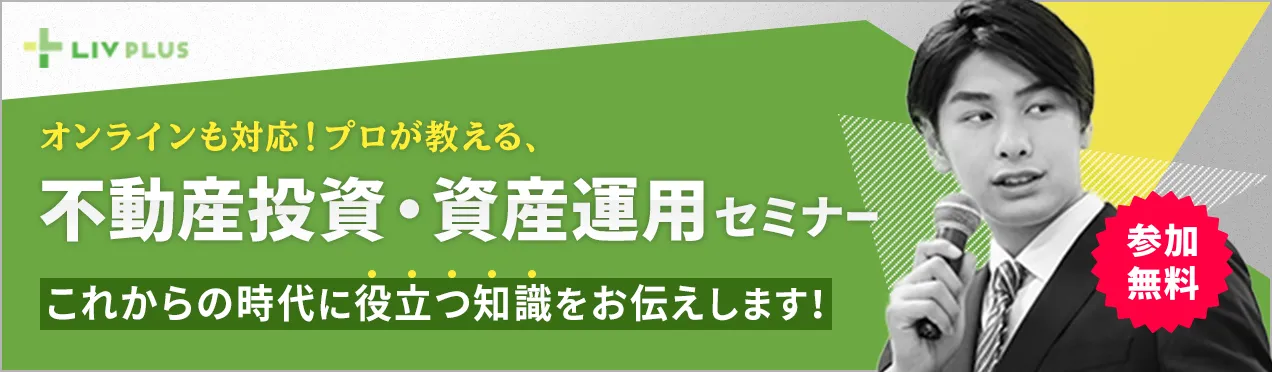
.png)
.png)