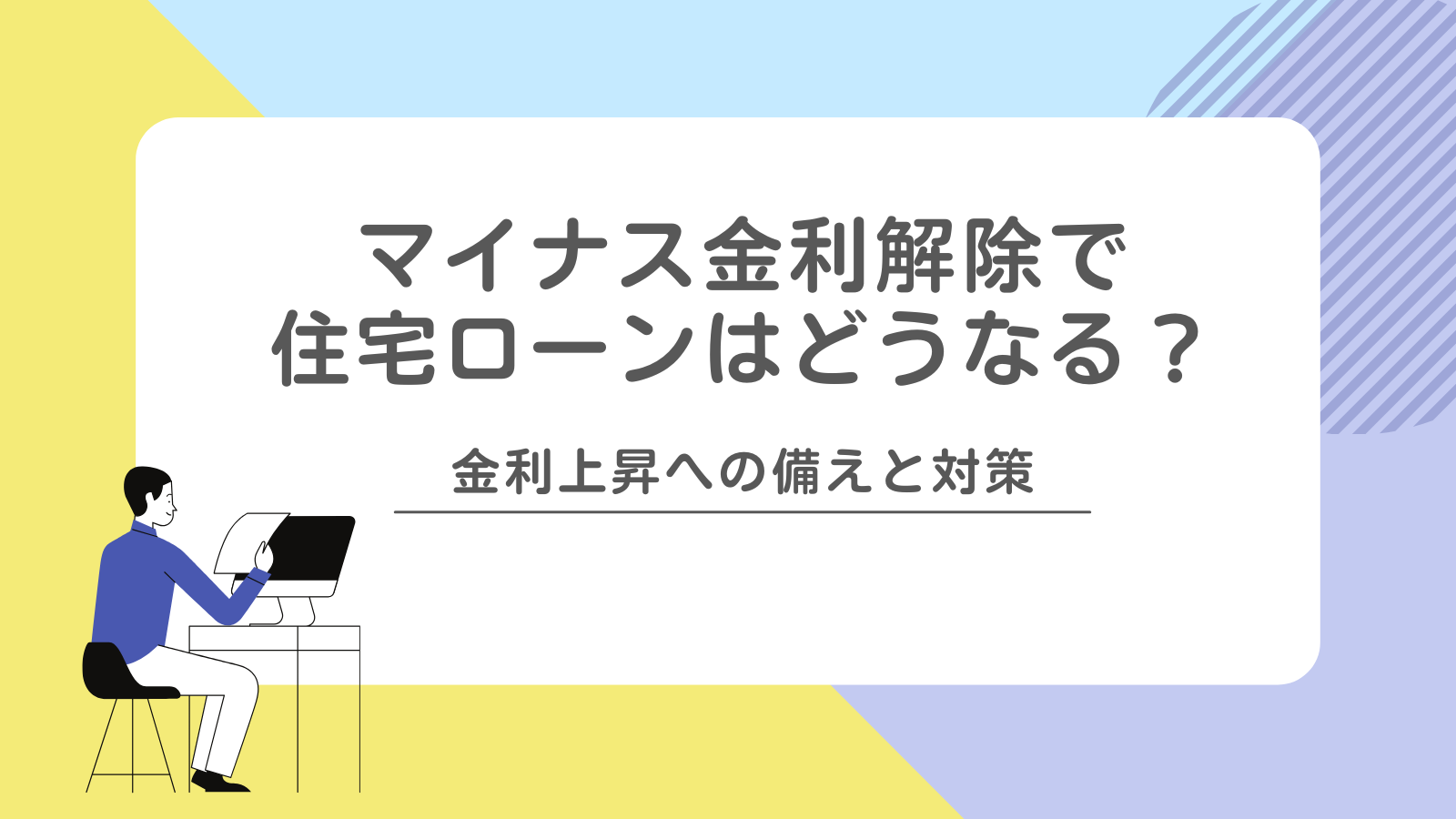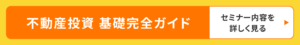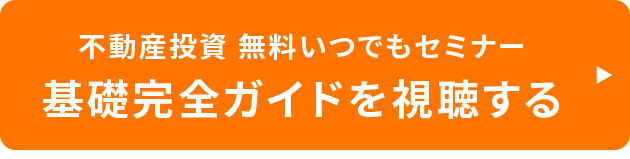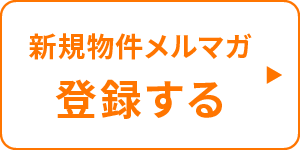2024年3月、日本銀行は17年ぶりにマイナス金利政策を解除し、政策金利の引き上げを決定しました。
さらに、2025年1月24日には、日銀は政策金利を0.25%引き上げ、0.5%としました。
そして、2025年3月18-19日の金融政策決定会合では、政策金利を0.5%程度に据え置くことを決定しました。この一連の動きは、私たちの生活にどのような影響を与えるのでしょうか?
特に、住宅ローンを利用している方、これから住宅購入を検討している方にとっては、今後の金利動向が大きな関心事となるでしょう。
本記事では、マイナス金利解除と政策金利引き上げが住宅ローンに与える影響、金利上昇への備え、そして賢い住宅ローンの選び方について、最新情報(2025年3月時点)も交えながら詳しく解説します。
マイナス金利解除とは?住宅ローンへの影響をわかりやすく解説

マイナス金利政策の基礎知識とその目的
マイナス金利政策とは、2016年に日本銀行が導入した金融緩和策の一つです。その目的は、長引くデフレからの脱却と経済成長の促進でした。具体的には、金融機関が日銀にお金を預ける際に金利をマイナスにすることで、金融機関が企業や個人への融資を増やし、経済活動を活発化させようとするものです。
デフレとは、物価が継続的に下落する現象です。物価が下がると、消費者は「もう少し待てばさらに安くなるかもしれない」と考え、買い控えが起こりやすくなります。企業も、売上が伸び悩み、投資や賃上げに消極的になるため、経済全体が停滞してしまうのです。
なぜ今、マイナス金利解除?その背景と理由
日銀がマイナス金利解除に踏み切った主な理由は、2%の物価安定目標の達成が見えてきたことです。長らくデフレに苦しんできた日本経済ですが、2022年以降、物価上昇の兆しが見え始めました。また、賃上げの動きも広がりつつあり、日銀は「物価と賃金の好循環」が生まれつつあると判断しました。
加えて、世界的な金融引き締め(金利上昇)の流れも、今回の決定に影響を与えたと考えられます。主要各国がインフレ抑制のために金利を引き上げる中、日本だけがマイナス金利を維持すると、円安が加速し、輸入物価の上昇を招く恐れがあります。
マイナス金利解除で住宅ローンはどうなる?
マイナス金利解除、そして政策金利の引き上げによって、最も直接的な影響を受けるのが住宅ローン金利です。金利が上昇すると、住宅ローンの返済額が増加する可能性があります。特に、変動金利型住宅ローンを利用している方は注意が必要です。
ただし、金利上昇の幅やスピードは、今後の経済状況や日銀の金融政策によって変わってきます。急激な金利上昇は景気を冷やす恐れがあるため、日銀は慎重に政策運営を行うと考えられます。
住宅ローン金利の現状と今後の見通し
変動金利型住宅ローンの現状と注意点
変動金利型住宅ローンは、多くの金融機関で、マイナス金利解除後や2025年1月の政策金利引き上げ後も、引き続き低い水準に据え置かれています。しかし、これはあくまで「当面の間」であり、今後の金利動向によっては、上昇に転じる可能性があります。特に、2025年以降、緩やかな上昇が予測されています。
変動金利型住宅ローンは、一般的に半年ごとに金利が見直され、5年ごとに返済額が調整されます(5年ルール)。また、返済額が増加する場合でも、元の返済額の1.25倍までとするルール(125%ルール)が設けられていることが多いですが、金利上昇が続けば、未払い利息が発生する可能性もあります。
変動金利は、日銀の政策金利(短期金利)の影響を強く受けます。2025年1月には政策金利が引き上げられましたが、一部の銀行では、2025年4月から変動金利の基準金利を引き上げることが発表されています。今後、他の金融機関も追随する可能性があるため、注意が必要です。
固定金利型住宅ローンの現状と注意点
固定金利型住宅ローンは、変動金利型よりも先に上昇する傾向があります。これは、固定金利が長期金利(10年物国債の利回りなど)を指標としているためです。マイナス金利解除後、長期金利は上昇傾向にあり、それに伴い、固定金利型住宅ローンの金利も上昇しています。特に、固定期間選択型(10年)や全期間固定型(35年)の金利は上昇傾向にあります(2025年3月時点)。
固定金利型住宅ローンは、金利上昇リスクを避けたい方、返済計画を安定させたい方に適しています。しかし、変動金利型に比べて、当初の金利は高めに設定されていることが多いです。
金利上昇が予測される要因
- ・世界的な物価上昇: 世界的なインフレ圧力は、日本の金利にも上昇圧力をかけます。
- ・賃上げの動き: 賃上げが進むと、消費が活発化し、物価上昇を招く可能性があります。
- ・国債の利回り上昇: 国債の利回りが上昇すると、住宅ローン金利、特に固定金利の上昇につながります。
- ・金融機関の貸出金利上昇: マイナス金利解除や政策金利引き上げにより、金融機関の貸出金利が上昇する可能性があります。
住宅ローン選びの戦略:変動金利 vs 固定金利
金利上昇局面では、住宅ローンの選び方がより重要になります。変動金利と固定金利、それぞれのメリット・デメリットを理解し、自身のライフプランやリスク許容度に合った選択をすることが大切です。
変動金利を選ぶメリット・デメリット
メリット:
- ・当初の金利が低い
- ・金利が下降局面では返済額が減少する
デメリット:
- ・金利上昇局面では返済額が増加する
- ・返済計画が立てにくい
- ・未払い利息が発生する可能性がある(5年ルール、125%ルールがあるが、金利上昇が継続すると元本が減らない可能性がある)
固定金利を選ぶメリット・デメリット
メリット:
- ・返済額が一定で、返済計画が立てやすい
- ・金利上昇リスクを回避できる
デメリット:
- ・当初の金利が変動金利より高い
- ・金利が下降局面でも返済額は変わらない
ライフプランに合わせた住宅ローンの選び方
住宅ローンを選ぶ際は、以下の点を考慮しましょう。
- ・返済期間: 返済期間が長いほど、金利変動の影響を受けやすくなります。
- ・収入の見通し: 今後の収入増が見込める場合は、変動金利のリスクをある程度許容できるかもしれません。
- ・リスク許容度: 金利変動による返済額の増加をどの程度まで許容できるか、自身の考え方を整理しましょう。
金利上昇への備えと対策:今すぐできること

金利上昇に備えて、今からできる対策を具体的にご紹介します。
家計の見直しと節約
まずは、家計簿をつけ、毎月の収支を把握することから始めましょう。無駄な支出を洗い出し、節約できる部分がないか検討しましょう。固定費(通信費、保険料など)の見直しは、効果が大きい場合があります。
繰り上げ返済の検討
余裕資金がある場合は、繰り上げ返済を検討しましょう。繰り上げ返済には、返済期間を短縮する「期間短縮型」と、毎月の返済額を減らす「返済額軽減型」があります。どちらを選ぶかは、自身のライフプランや家計状況によって判断しましょう。
借り換えの検討
現在、変動金利型住宅ローンを利用している方は、固定金利型への借り換えを検討するのも一つの方法です。金利が上昇する前に借り換えることで、金利上昇リスクを回避できます。ただし、借り換えには諸費用がかかるため、費用対効果を慎重に検討する必要があります。
【借り換え検討時の注意点】
- ・借り換えには諸費用(事務手数料、保証料、印紙代など)がかかる
- ・自身の信用情報を確認する(クレジットカードの支払遅延などがあると、審査に通らない場合がある)
- ・複数の金融機関の条件を比較検討する
- ・金利動向を見極める(金利が上昇傾向にある場合は、早めに借り換える方が有利な場合がある)
専門家への相談
住宅ローン選びや借り換えは、専門的な知識が必要な場合が多いため、金融機関の担当者やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することをおすすめします。専門家は、個別の状況に合わせたアドバイスやシミュレーションを提供してくれます。
相談する際は、複数の専門家の意見を聞き、比較検討することが重要です。また、専門家の経歴や実績を確認し、信頼できる相手を選びましょう。
まとめ:マイナス金利解除後の住宅ローン戦略
日銀のマイナス金利解除、そして政策金利の引き上げは、住宅ローン市場に大きな影響を与える可能性があります。しかし、適切な知識と対策があれば、この変化を乗り越え、賢く住宅ローンを利用することができます。
本記事で解説した内容を参考に、
- ・自身の住宅ローン契約内容を確認する(特に金利タイプ)
- ・金利タイプ(変動金利・固定金利)のメリット、デメリットを理解する
- ・家計の見直しや繰り上げ返済、借り換えを検討する
- ・必要に応じて専門家に相談する
といった行動を、今すぐ始めましょう。変動金利を利用中の方は、特に金利上昇リスクに注意し、早めの対策を検討しましょう。
当社では、不動産投資に関する無料セミナーを定期的に行なっております。お気軽にご参加ください。
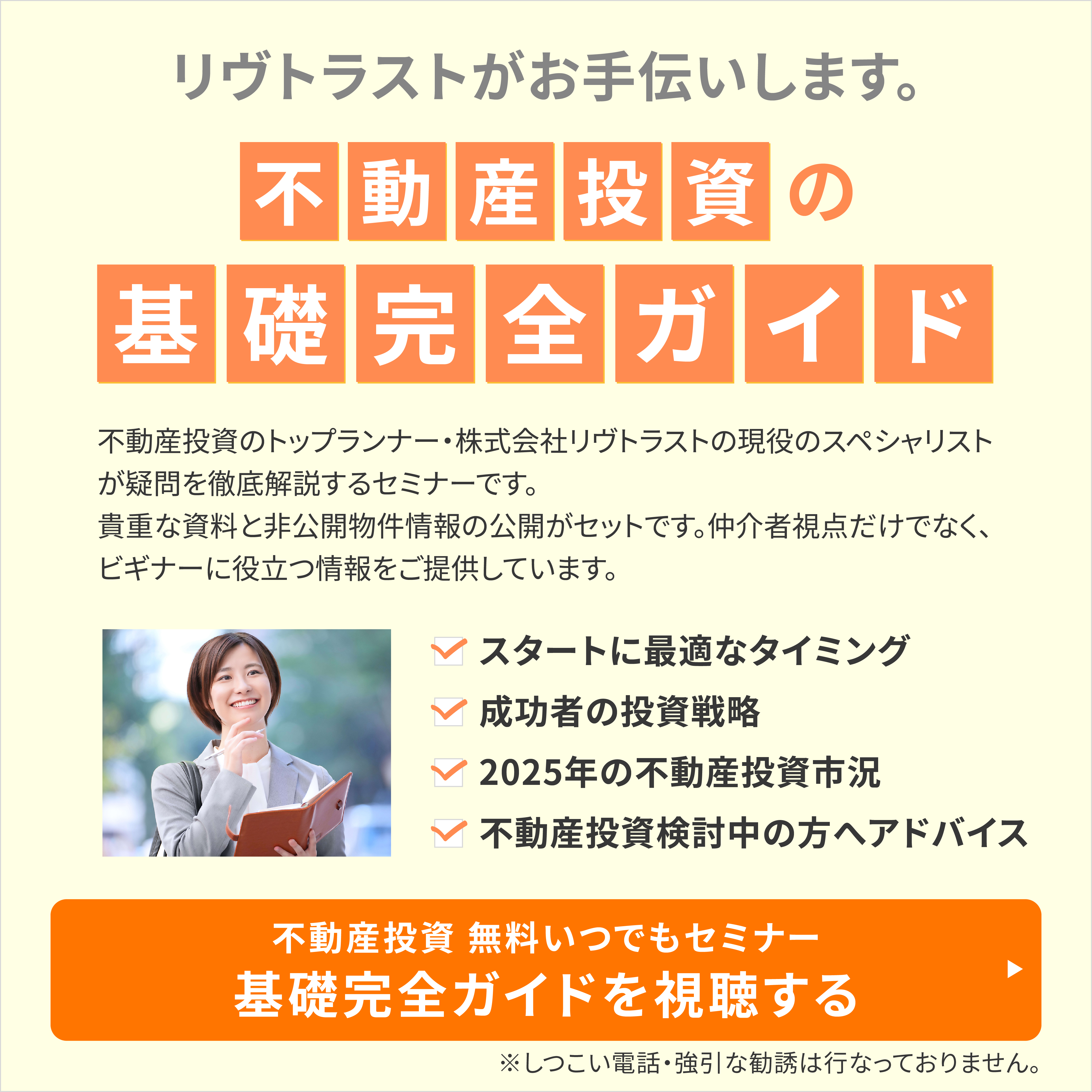

また、メルマガでは、新着コラムや最新ニュースのご案内、一般公開前の限定物件のご紹介などを配信しております。ぜひご登録ください!