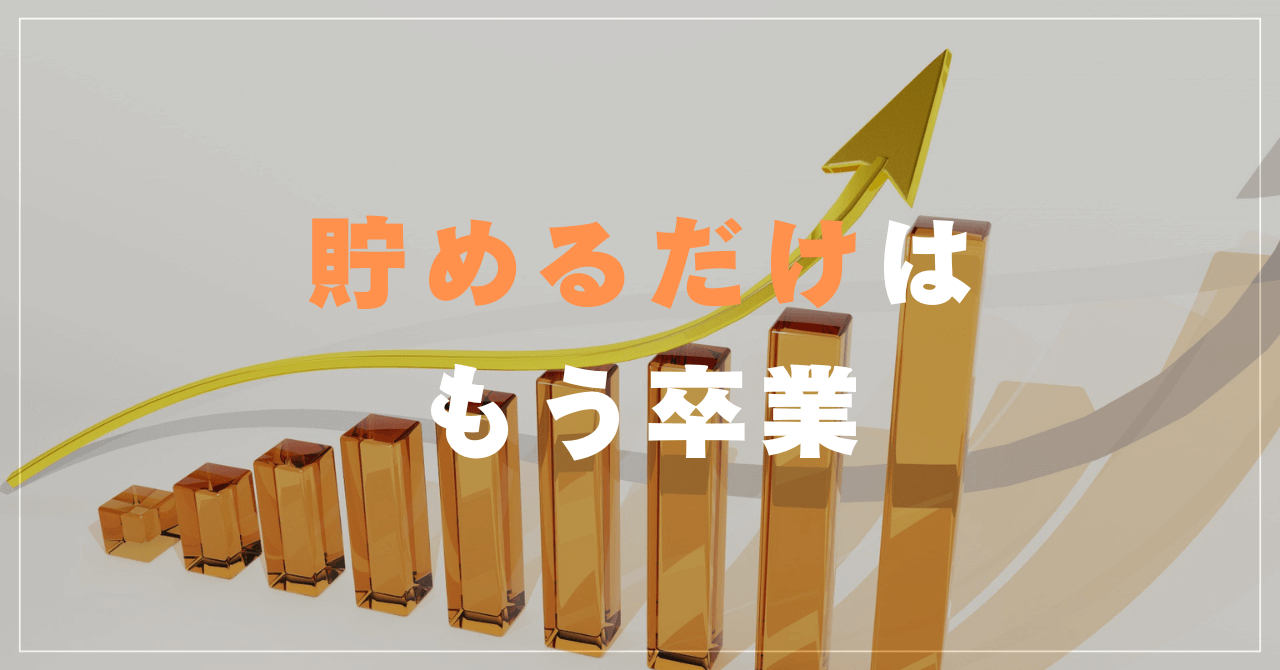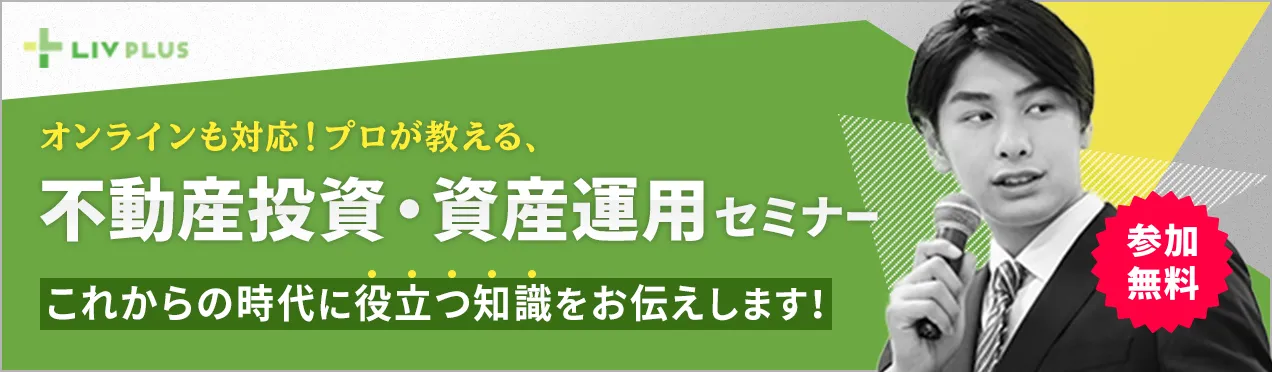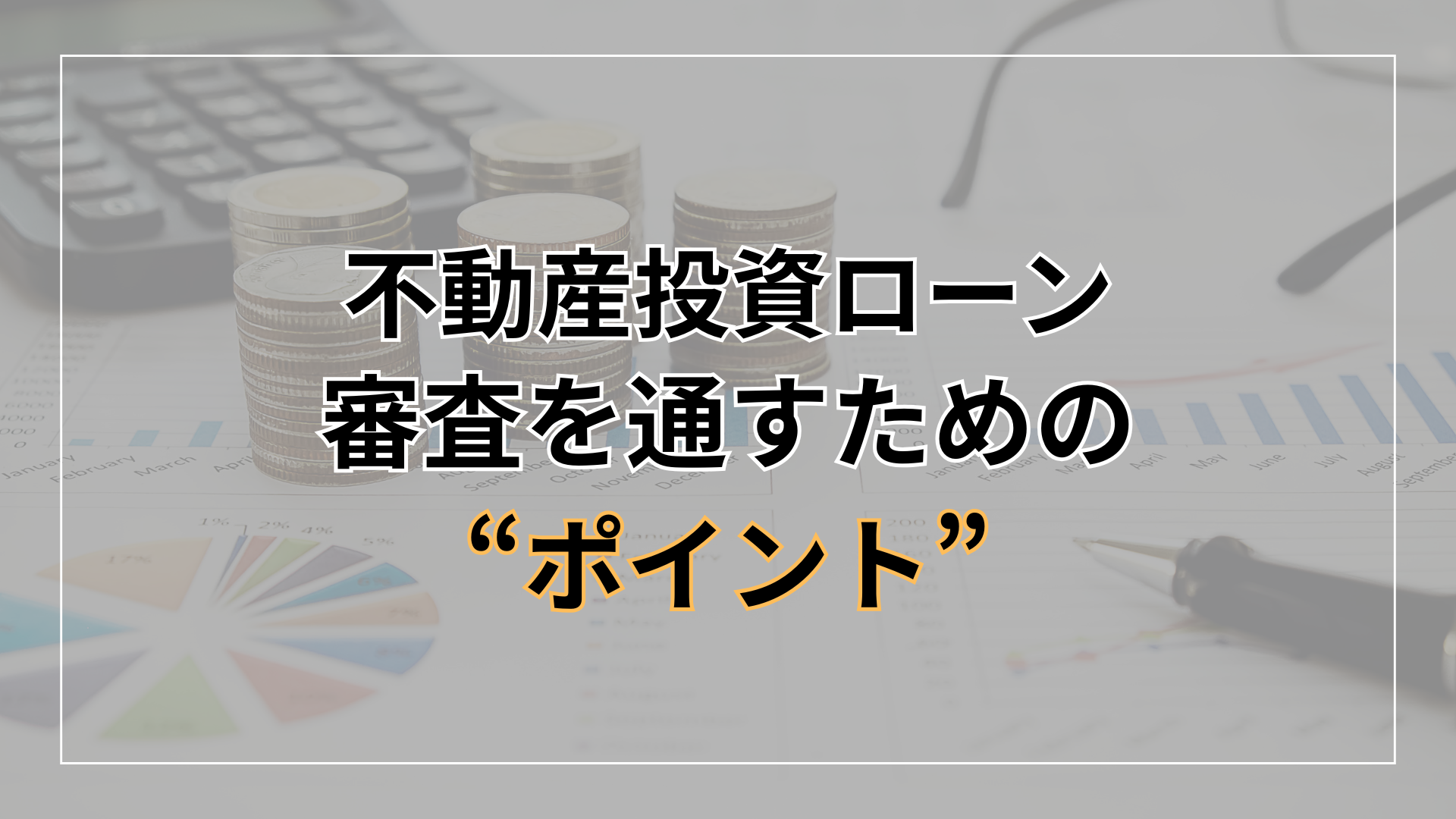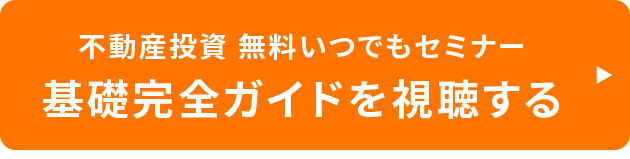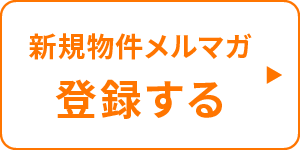本日10月17日は「貯蓄の日」。将来のために、毎月コツコツと貯金を続けてきたあなたは、本当に素晴らしい努力をされています。その貯金は、あなたの人生を守るための、かけがえのない「守りの資産」です。
しかし、その大切なお金、ただ銀行に預けておくだけで、本当に“守り切れる”でしょうか?
近年の物価上昇(インフレ)により、去年100円で買えたものが、今年は103円出さないと買えなくなっています。これは、あなたの貯金の価値が、何もしなくても実質的に目減りしていることを意味します。
「貯蓄の日」である今日を機に、これまでの「守る貯金」から一歩進んで、インフレに負けずにお金を「育てる資産」へと進化させる、具体的な第一歩を、ゼロから分かりやすく解説します。
まずは大前提:「貯蓄」は資産形成の“最強の土台”です
資産を「育てる」話の前に、まず大前提として「貯蓄」の重要性を強調させてください。
万が一の失業や病気に備えるための「生活防衛資金(生活費の6ヶ月〜1年分)」を確保することは、何よりも優先すべきことです。これが、安心して資産形成という次のステージに進むための“心の安全網”になります。
あなたがこれまで築き上げてきた貯蓄は、決して無駄ではありません。それは、未来の資産を育てるための、最も重要で、最も頑丈な土台なのです。
なぜ今「貯蓄だけ」では危険なのか?インフレの正体
では、なぜその頑丈な土台の上に、次の家を建てなければならないのでしょうか。それは「インフレ」という、お金の価値を静かに蝕む存在がいるからです。
【現実】金利 vs 物価上昇
普通預金金利:年 0.001%
物価上昇率:年 3%前後
「100万円を1年預けても利息は10円。
でも、世の中のモノの値段は3万円も上がってしまう」
政府が「貯蓄から投資へ」というスローガンを掲げ、新NISAを始めた背景には、私たち一人ひとりがインフレに負けない資産作りをしなければ、豊かさを維持するのが難しい時代になった、という強いメッセージが込められています。
昇給が物価上昇に追いつかず、社会保険料の負担は増え続ける—。
これが、今の日本で働く私たち現役世代が直面している、厳しい現実です。もはや、給与収入だけで将来の安心を確保するのは、極めて困難な時代になったと言わざるを得ません。
だからこそ、「貯蓄」という守りの土台の上に、自ら資産を育てていく「資産形成」が、特別なことではなく、未来の自分と家族を守るための“必須科目”になったのです。
「貯蓄から資産形成へ」具体的な3ステップ
「育てる」と言っても、何から始めればいいのでしょうか。焦る必要はありません。以下の3ステップで、考えを整理してみましょう。
STEP 1目標を決める
「なぜお金を増やしたいのか?」を明確にします。(例:30年後の老後資金、10年後の子供の教育費、5年後の住宅購入の頭金など)。目標までの期間が、あなたに合った方法を教えてくれます。
STEP 2選択肢を知る
NISA(少額投資非課税制度)、株式投資、不動産投資など、様々な選択肢があります。それぞれにメリット・デメリットがあります。
STEP 3自分に合った方法を選ぶ
あなたの投資期間、リスクに対する考え方、そして「どれくらい手間をかけられるか」を元に、どの方法が最適か考えてみましょう。
【結論】忙しい会社員に「不動産投資」が最適な理由
NISAや株式投資も、もちろん素晴らしい資産形成の手段です。しかし、日々の株価の変動に一喜一憂したり、世界経済のニュースを常に追い続けたりするのは、多忙な会社員にとって、時に大きな負担になり得ます。
私たちリヴトラストは、これまで数多くの会社員の皆様の資産形成をサポートしてきましたが、その中で多くの方が最終的に不動産投資を選ばれるのには、明確な理由があります。
それは、不動産投資が、日々の値動きに振り回されることなく、安定した家賃収入(インカムゲイン)を長期的に得られるという、他の投資にはない大きな魅力を持つからです。
まさに「時間を味方につける」という資産形成の本質を、最も体現しやすい手法なのです。
まとめ:「貯蓄の日」は、お金の“置き場所”を考える日
素晴らしい「守る貯金」という土台は、すでにあななたの手の中にあります。しかし、インフレという時代の変化の中で、そのお金の“置き場所”を少し変え、「育てる資産」という視点を持つだけで、未来は大きく変わります。
「貯蓄の日」である今日を、ただ貯めることから、賢く守り、そして育てていく「資産形成」元年にしませんか?その第一歩が、あなたの10年後、20年後の生活を、より豊かで安心なものに変えるはずです。
あなたの「貯蓄」を、どう「資産」に変えていくか、
一緒にシミュレーションしませんか?
「自分にはどのくらいの資産が築けるんだろう?」
「まずは何から始めればいい?」
そんな疑問に、プロが具体的にお答えします。