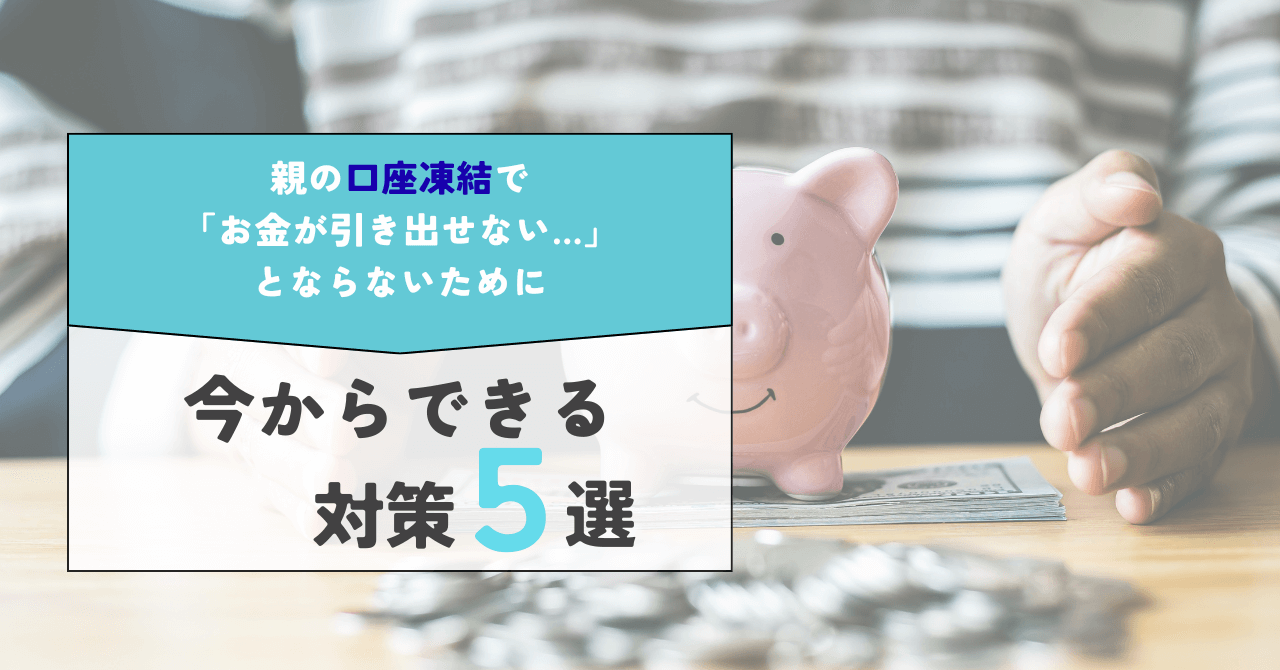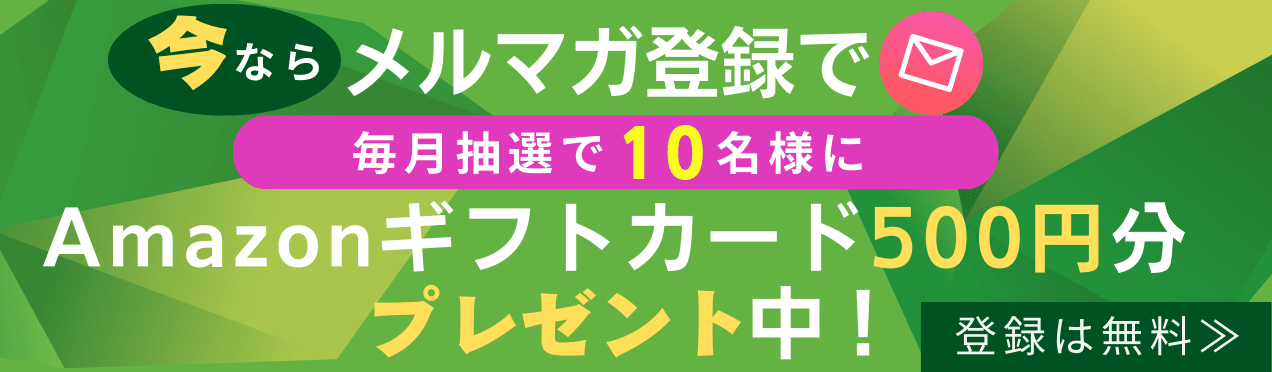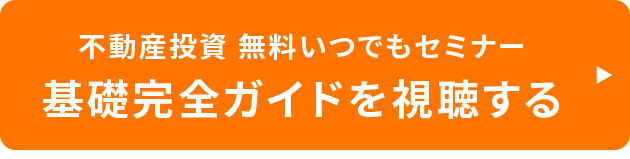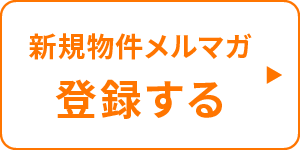「親の預金口座が突然凍結…」
ニュースでたまに見るこの言葉、まだ遠い未来の話だと思っていませんか?
実は、認知症だけでなく、親が急な事故や病気で倒れただけでも、口座は凍結され、家族でも預金が引き出せなくなるケースが急増しています。
「介護費用や入院費が払えない」「実家の光熱費が引き落とせない」…そんな“まさか”の事態に、親族が貯金を切り崩して立て替えるケースも。ある調査では、凍結リスクのある金融資産は9兆円にものぼると言われています。
この記事では、そんな「もしも」の時に家族が困らないために、親が元気なうちに、子として準備しておける具体的な5つの対策を、簡単なものから本格的なものまで、分かりやすく解説します。
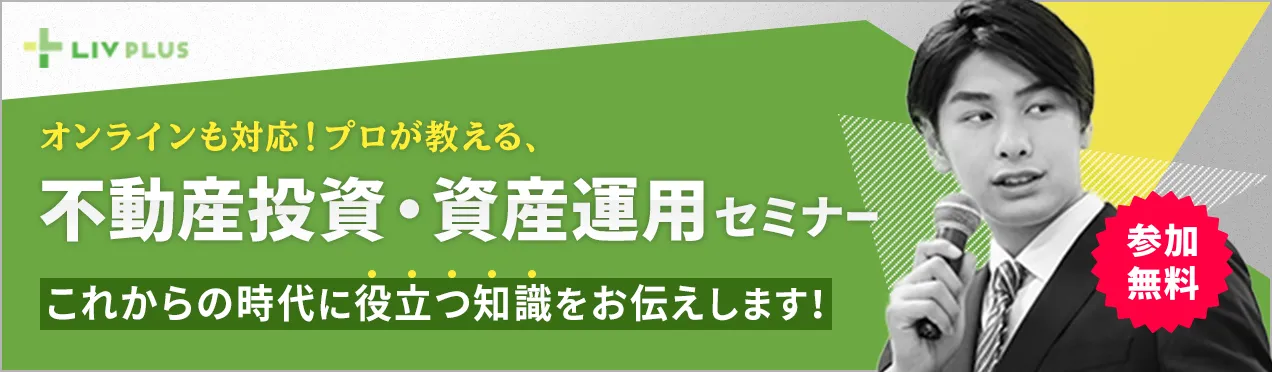
●開催中のセミナー詳細はこちら
📖この記事の目次
なぜ親の口座は凍結される?知っておくべき「資産凍結リスク」
そもそも、なぜ銀行は口座を凍結するのでしょうか。それは、詐欺や相続トラブルなどから、預金者本人の財産を守るためです。
銀行が、預金者本人の「意思能力」が低下したと判断した場合(例えば、認知症の診断を受けた、事故で意識不明になったなど)、財産を守るために口座からの出金をストップします。これが「口座凍結」です。一度凍結されると、たとえ家族であっても、原則として預金を引き出すことはできません。
【今日からできる】まず始めたい「誰でも簡単にできる対策」3選
まずは、比較的すぐに、家族だけで実践できる対策を3つご紹介します。
① 親のキャッシュカードを使えるようにしておく
親の同意を得た上で、カードの保管場所と暗証番号を共有しておく方法です。最も手軽ですが、注意点もあります。他の兄弟など親族間の合意がないと、「勝手にお金を使ったのでは?」という相続トラブルに発展しかねません。この方法を取る場合は、必ず親族全員の合意を得て、いつ、何のために、いくら引き出したのかを1円単位で記録・共有することが鉄則です。
② 金融機関の「代理人制度」を利用する
多くの金融機関には、口座名義人が元気なうちに、代理人を指名できる制度があります。この手続きをしておけば、万が一の時に、指名された代理人(子など)が堂々と銀行窓口やATMで手続きを行えます。金融機関によって制度の有無や内容が異なるため、まずは親が利用している銀行や証券会社に問い合わせてみましょう。
③ 年金口座と生活費口座をまとめておく
口座が凍結されても、年金の振り込みや、そこからの公共料金などの引き落としは継続されるケースが多いです。そのため、年金が振り込まれる口座と、家賃や光熱費などが引き落とされる口座を同じにしておくだけで、最低限のライフラインが止まる事態を防げます。複数の口座を管理している場合は、この機会に一本化を検討してもらいましょう。
【不動産など大きな資産を持つ方へ】専門家と進める本格的な対策2選
ここからは、より確実性が高く、特に不動産などの大きな資産を守るために有効な、専門家を交えた対策です。
④「生前贈与」で計画的に資産を移す
親が元気なうちに、子や孫へ計画的に財産を贈与していく方法です。年間110万円までなら非課税で贈与できる「暦年贈与」が有名で、相続税対策としても有効です。ただし、「名義預金」とみなされて贈与が認められないケースなど、税務上のルールが複雑なため、実行する際は必ず税理士などの専門家に相談しましょう。
⑤「家族信託」と「成年後見制度」を比較・検討する
これらは、特に不動産などの大きな資産を管理するために用意された、より強力な法的制度です。どちらも専門家への相談が必須となりますが、基本的な違いを理解しておきましょう。
一目でわかる「家族信託」と「成年後見制度」の比較表
| 項目 | 家族信託 | 成年後見制度 |
|---|---|---|
| 目的 | 財産管理・運用、相続対策 | 本人の財産保護、身上保護 |
| 開始時期 | 本人が元気なうち | 判断能力低下後 |
| 財産管理人 | 家族がなれる | 裁判所が選任(専門家が多い) |
| 柔軟性 | 高い(積極的な資産活用も可) | 低い(財産維持が原則) |
| コスト | 初期費用は高め、継続費用は低い | 初期費用は低め、継続費用が高い |
「家族信託」のメリット・デメリット
メリット: 親が元気なうちから、信頼できる家族を財産管理人に指定できます。契約内容によっては、相続税対策や積極的な資産活用といった、柔軟な財産管理が可能です。
デメリット: 初期費用が高額になりがちな点、介護契約などの身上保護は対象外である点、そして信託した不動産で損失が出ても他の所得と損益通算ができない点には注意が必要です。
「成年後見制度」のメリット・デメリット
メリット: 財産管理だけでなく、介護や医療に関する契約(身上保護)まで幅広く本人を保護できます。また、本人が結んでしまった不利益な契約を取り消せるなど、非常に強力な法的権限を持ちます。
デメリット: 財産は本人の利益保護のためにしか使えず、積極的な資産活用や相続税対策はできません。一度始めると原則途中でやめられず、専門家が後見人になった場合は継続的な報酬が発生します。
まとめ:一番の対策は、親子で「お金の話」をすること
ここまで5つの対策を紹介してきましたが、どんなテクニックよりも重要なことがあります。
それは、親子関係が良好で、お金の話をオープンにできる環境を、親が元気なうちに作っておくことです。
「相続」や「認知症」という言葉は、どうしても切り出しにくいものです。
しかし、これは「親の資産」の話ではなく、「家族みんなの将来を守るため」の話です。この記事をきっかけに、「万が一の時に困らないように、一度話しておかない?」と、愛情をもって話し合う時間を作ってみてはいかがでしょうか。